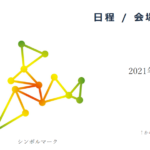2021年度建築学会大会
2021年度の日本建築学会大会では、歴史意匠の研究協議会「戦後昭和の建築―その価値づけをめぐってー」で権藤が構法分野からプレハブ住宅と高層ビルについて主題解説を行いました。下の方に全文(図版なし)を載せておきます。資料集は200ページ近くの力作なので是非手に取って見てみてください。図版見たくなった人は買ってください。
https://www.aij.or.jp/taikaikenkyu/
また、構法史のオーガナイズドセッションも開催され、谷繁が「1970 年代 – 80 年代の日本の工業化住宅構法の変化に関する研究」、千葉が「1950 〜 60 年代の日本の RC シェル建築の施工法に関する研究」を発表しました。構法史もりあがってきております。他にも研究室関係の連名が数題ありました。
戦後日本の工業化住宅と高層建築における構法的な価値
1.本音と建前
建築にも本音と建前があるとすれば、構法や施工は本音に近い分野と言えるのではないか。建築や部位が何故そうなったかはコストや職人のレベル、他の材料が手に入らないといった理由から決まることも多いが、こうした本音は記録には残りにくい。インタビューをしていて、「そんな理由ですか、これは書けませんね」という話になる。それでは本音に価値がないかといえばそうではない。普段生活している建築がなぜこのようになっているかを理解することは根源的な欲求であり、発見的な面白さがある。その知識が役に立つかどうかではなく、その知識によって見える光景が変わるところに価値がある、というのが偽らざる本音である。
以下では、構法・施工的な側面から戦後多くの技術開発がなされた高層建築と工業化住宅、プレハブ住宅を例にとって、その歴史的な価値やそれを知る上での課題などについて施工写真等の図版や文献・資料に残された証言を交えながら考えてみたい。以下、「構法」は建築の物的な構成方法として用い、施工(工法)と併記しない場合は、「構法」にその実現する過程、いわゆる施工法(工法)も含める場合もある。さらに躯体を施工することを建前とも呼ぶのでやや注意を要する。
2.一対多
写真1は戦後、オランダ、フランスで建設されたポルト・デ・リラ工法の施工風景である。細長い平面を奥側から順に建てて行く建て逃げの工法で建てられている。1階から最上階までの柱と2層毎の梁の鉄骨を地上で組んでしまい、一気に建て起したティルトアップ工法の大がかりな例である。これによって危険な高所作業を減らし、工期短縮も実現するのが目的と考えられる。学生時代の講義で印象に残ったこの建築でさらに印象的なのは竣工後の姿である(写真1下)。一見すると千鳥に塗装された普通の集合住宅である。これは当たり前で、鉄骨のフレームにプレキャストコンクリート(以下、PCa)やサンドイッチパネルの床や壁を配置していく工法は、できあがってしまえばその見た目は在来の鉄筋コンクリート壁式の建築とも変わらなくなる。構法面の特徴を意匠的に強調することはありえたかもしれないが、それは生産性を重視したであろうこの工法の特質と相容れない。
構法的な価値やその保存を考える時、問題になるのはこうした建築だと思われる。構法的には独自性の高い工夫が見られる一方で、完成した建築の見た目にそれほど特徴がない。ポルト・デ・リラを見て分かるように、ある建築や部位を構想した場合、それを実現する構法は通常一種類ではない。戦後、構法学が始まった時点に遡れば、こうした「一対多」の関係に対応するために構法学は生まれた。構法学における草創期のモチベーションは、構法をリスト化する構法論と要求条件を定量的に定める性能論を突き合わせて合理的に構法を決定することであった。これは構法学以前の一般構造、各部構造分野において前提とされた構法の定石が崩れたことが背景にある。戦前までの構法はある部位に対して、ある程度「定石」として構法が導き出された。「ある条件のこの部位には標準的(定石的)にはこの構法が使われる」といった一対一に近い関係である。それが戦後になって、海外から新建材が導入されたり、新たな構法の開発が行われるようになり、この部位と構法との関係が安定的ではなくなった。同様に施工法についてもプレハブや機械化などつくり方が多様になっていく。こうした建築と技術の一対多の関係は、技術開発が途切れなく続いた戦後建築生産の特徴とも言えるし、この一対多の関係によって、技術的に特徴のある建築であっても見た目からは分からないといったことが起こりえる。
図1右は霞が関ビルディング(1968年、鹿島建設・三井建設施工)で使われたキの字の鉄骨である。通常は図1左側のように柱に短い接合用のブラケットを取り付け、それと梁を接合する。一方、霞が関ビルディングは柔構造を採用し、外周に柱が3.2mという短い間隔で並ぶ。そのため、ブラケットを伸ばして直接接合するキの字の鉄骨が用いられた。これにより、輸送の手間は増えるが、接合部の数は半減し、短い梁をクレーンで揚重する必要もなくなった。霞が関ビルディングの施工においては工期短縮のために「基準階繰り返し」がテーマとされ、各工程を1層につき6日で統一し、作業の無駄や待ち時間が出ないようにした。キの字の鉄骨は各工程にかかる時間を短縮する代表的な工夫である。
この工法を発展させたのがホテルニューオータニタワー(1974年、大成建設施工、写真2)である。ホテルニューオータニタワーの外周柱もキの字で組まれているが、外周1本おきに高い柱、短い柱が並ぶ。これによって、次に施工する柱は下の柱だけでなく、横の梁とも接合されて安定する(3点で支持される)。なお通常の高層ビルでは運搬面から3層1節の柱が多いが。ホテルニューオータニタワーでは3点支持のため2層1節となった。可能な限り1層おきに施工を完結させるのは、大成建設独自の積層工法の特徴でもある。ただし、鉄骨をキの字にしようが、千鳥に組もうが、2層1節にしようが、組み上がった鉄骨の見た目はほとんど変わらない。尚、写真右上、床の上に四角い箱が見えるが、これはPCaのユニットバスである。
工業化住宅においても、躯体において大きなトライアルをおこなったが見ても分からないものがある。1つの代表例がトヨタホームKC型だろう(1977年、写真3)。これはセキスイハイムM1等と同じく箱型のユニットを採用している。驚くべきはこの柱・梁からなるユニットが鉄筋コンクリートにより、しかも一体で打設されていることである。竣工した写真3右を見ると、柱・梁が強調されているようにも見える。しかし、よほどのマニアでない限り壁の入った後のKC型やその構法的な特徴に気づく人はいないであろう。このように構法的に特徴がある建築には、最終的な外観というよりも、そのつくり方に創意工夫が見られるものがあり、完成後の外観からその工夫が伝わらないものが多い。
3.普及へ
写真4は現在プレハブ住宅最大手である積水ハウスの最初の住宅商品セキスイハウスA型(1960年)である。この前年に大和ハウスからミゼットハウスが売り出されているが、現在も住宅供給を行う大手プレハブ住宅メーカーの住宅商品で風呂、トイレを備えたものは、セキスイハウスA型が初めてである。セキスイハウスA型の特徴は、屋根・外壁のアルミサンドイッチパネル、妻面に設けられた塩化ビニルの庇兼袖壁、スチールサッシなどである。また、設計者の石本徳三郎が考えた3ヒンジアーチ構造に従い、室内天井は船底天井で外観全体もかまぼこ形をしており、室内壁・天井取り合い部には三角形のハンチが露出する。
2016年、長野県軽井沢町に現存するセキスイハウスA型が工業化住宅として初めて有形文化財(建造物)として登録された。登録に関しての文化庁の文書には、「居室と水まわりを備えた本格的な工業化住宅の国産第一号」と書かれており、「ほぼ完存するセキスイハウスA型としては国内唯一の遺構で、我が国の戦後住宅業界の一側面を語る」注1としている。尚、後述するように登録されたセキスイハウスA型には、上記のような外観上の特徴はほとんど残っていない。屋根は鋼板に改修されており、庇が両方向に出され視覚的にも切り妻屋根が強調されている。塩ビの庇や袖壁もなくなっている。
セキスイハウスA型が戦後住宅業界の一側面を語ることに異論はないが、積水ハウスにおける現在の構法の主流はA型の次のB型である(写真5)。A型発売の翌1961年に開発されたB型の特徴は柱・壁と小屋組トラスの分離であり、より普遍的な「住宅らしい」外観にある。これが多様な条件・要望に合わせた工業化住宅生産を可能にし、年間数千棟、数万棟の販売につながった。このように、最初期の「プレハブらしい」住宅からより「住宅らしい」外観への変化やより対応範囲の広い構法への変化は積水ハウス以外の大手プレハブ住宅メーカーでも初期に確認できる。
たしかに戦後多くの日本人が暮らした工業化住宅の原点の1つにセキスイハウスA型はあるが、「多くの日本人が暮らした」点に焦点をあてればB型により価値をおくことも可能と言える。しかし、B型を使った住宅は見た目に特徴が乏しい。また、軽井沢にやっと1棟残っていたA型と違い、日本全国津々浦々に建ちすぎている。大量供給という当初の目的を実現した住宅は1棟あたりの価値は低下せざるをえないとも言えよう。このようにプレハブ住宅初期の手作業的なトライアルを示しているA型に対し、B型はシステマチックな大量供給を可能にした原型と呼ぶべきものである。そしてこの対照的な両者間の移行のプロセスに、プレハブ住宅産業が自走し始める契機を読み取れる。
一方で近年、都市部を中心に多く供給されているのが高層集合住宅である。写真6は椎名町アパート(1974年、鹿島建設施工)である。地上18階、高さ54mは一般に高層建築の目安とされる60mを下回るが、Hi-RCと呼ばれる鹿島建設の高層RC(鉄筋コンクリート)造建築の開発はここに始まり、現在の高層マンションの先駆けとも言える。なお、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造)高層集合住宅としては三田綱町パークマンション(1971年、鹿島建設・三井建設施工)が2年前に竣工している。集合住宅の高層化に向けてはコスト、室内環境(遮音)の面から鉄筋コンクリート造の適用が検討されてきた。
写真6を見ると、柱がかなりの密度で立ち並んでいる。椎名町アパートにおける柱のコンクリート強度は1階から6階まで30N/mm²である。現在のような高強度コンクリートはない。そのため柱のスパンは3.0m×4.5mと現在からすればかなり短く、竣工後の建築はスレンダーな印象を受けるが、内部には制約が多い。現場打ちRCの欠点は型枠、配筋など現場作業の多さにあり、施工にあたってはプレハブ化が追求された。写真でクレーンが吊り上げているのは、KTS(Kajima Truss Shore)型枠である。梁の型枠と床の型枠を一体化し、下の階で脱型した後、一体化したまま上の階に吊り上げる。脱型し、床天井がある中でスライドさせ、つり出せるように工夫されている。他にも、柱の鉄筋は一般的な帯筋に加えて、主筋の内側に鹿島スパイラル筋と呼ばれる剪断補強筋が加えられ、柱と梁の接合部(パネルゾーン)の鉄筋には梁の上下の主筋をU型に連続させ、柱筋の間に通して定着させるなど、耐力向上、工期短縮の様々な工夫が見られる。現在の高層集合住宅では現場打ちRCとPCaとの組合わせで合理化が図られるが、椎名町アパートは現場打ちRCの合理化を徹底的に考えた建築と言える。
鹿島建設におけるその後の高層集合住宅PCa化の歩みも興味深い。パネルゾーンに穴の空いた蓮根PCaを基本として様々なPCa化を行っている。柱梁を3次元的に組み合わせてユニットにしたり、現場でPCaを製作できない場合には一方向に大きく梁を伸ばしたPCaを製作したりといった工夫を重ね、ローレルスクエア都島(2001年、鹿島建設ほかJV施工、写真7)では躯体工事2日/階という驚異的なスピードを実現する。そして、この驚異的なスピードによって「ギネスブック物だと喜んだのだが、あまりにも躯体工事スピードが速すぎ、後続の設備・仕上工事が追い付けず、躯体設備仕上が一体となった合理的な施工法とはいえないという笑えない現実に直面」注2することになった。前掲の霞が関ビルディングのように、「基準階繰り返し」の高層建築においては特定の工程のみ工期短縮しても全体の工期短縮にはつながらない。このように工業化住宅においても高層建築においても、初期や発展期には技術開発が集中的に行われ、その後社会に受け入れられていく中で、あるものは引き継がれ、あるものは使われなくなる。初期の現在から見れば過剰とも言えるトライアルにも、普及して残った構法にもそれぞれ別個の価値があると考えるのが妥当だろう。
4.説明必要
ここまでいくつかの施工写真を見てきたが、上記のような構法・施工の工夫を伝えるには、竣工後の写真や完成した建物の図面だけでなく、つくり方の工夫がビジュアルに伝わる資料ができればほしい。しかし、施工写真が建築雑誌等に掲載される機会は限られている。2001年までは施工の専門誌「建築の技術 施工」(彰国社)もあったが廃刊している。こうした施工写真は社史や社内誌など様々なところに分散している。 さらに言えば、こうした構法、施工の工夫は写真だけを見ても分からない場合が多い。冒頭のポルト・デ・リラのような工法であれば、施工写真を見ただけでその特徴が分かるが、そうした例は希である。写真8は竹中式潜函工法の東京での代表例、日活国際会館(1952年、竹中工務店施工)の施工写真である。現在、日比谷公園をのぞむこの敷地にはザ・ペニンシュラ東京が建つ。建設前の敷地は進駐軍の駐車場だった。
潜函とは地上で構築した函体を地中に埋設する工法である。これを建築全体の地下部分に適用し、地上で地下部分を構築した後でその直下を掘削し、徐々に構造物全体を沈下させるのが竹中式潜函工法である。写真を見ると、鉄骨の骨組の下に高さ3、4階分の白い壁が見える。これが潜函部分であり、これからこの下の地面を掘って建物全体を沈めていく。写真からは分からないが、地上でつくった建物を沈めていくために建物外周部の基礎は下に尖ったような形状をしている。この内側の地面を掘っていくと、あるところで重みに耐えられなくなり、尖った基礎が食い込むように建物全体が沈下する。尚、日活国際会館は地上9階地下4階、延床面積約48,000平米、外周は約300mあって竹中式潜函工法が使われた建築の中では最も大きい。さらに細長い3角形の敷地形状は不同沈下を起こしやすく管理には細心の注意を必要とした。竹中式潜函工法メリットは地上地下同時工事の工期短縮、地下部分の品質向上、騒音や振動の低減など色々あるが、敷地面積いっぱいの地下を構築できることであろう。ただし、1964年の容積率制の導入によって、地下を限界まで活用しようとする気運も薄れ、東洋工業社屋(1964年、竹中工務店施工)を最後に竹中式潜函工法も使われなくなったとされる。急沈下や不同沈下が危険なのも理由だろう。日活国際会館の第1回の急沈下では97センチの沈下が起こり、躯体は有楽町方向に少し傾いたとされる。「建築は金のかかる地下構築の代わりに、天空に向けて面積を積み上げることが可能になった注3」。
先ほどのキの字にも増して、竹中式潜函工法のように地下で革新的な技術が使われた場合、その技術が使われた痕跡を外部から確認することは難しい。さらに竹中式潜函工法の写真8に関して言えば、言われて初めて写真に地下部分が映っていることに気づく人も多いだろう。冒頭、見える光景が変わると書いたが、写真を見ていても見えるものが変わってくる。このように構法まで踏み込んで理解をするにはそれなりの資料に加えて、どこに工夫がなされていたのか、どのような意味があるのかといった証言も可能であればほしい。「金のかかる地下構築」のように当時の技術者の認識や実感も知りたい。工業化住宅や高層建築においてこうした証言が発表されることは少ないが、戦後に供給された建築においては、この証言を聞く機会がギリギリ残されている。
プレハブ住宅に関する証言を集めていた頃、他社を含めてよく名前があがったのがミサワホームO型(1976年、写真9)である。工業化住宅は量産を考えると標準設計や規格型に偏り画一的になり、販売数を増やそうとして自由設計を志向すれば量産の効果は薄れる。O型においてミサワホームは、積極的に独自の住宅の姿を提案する「企画住宅」という新たな方針を打ち出し、結果として日本の住宅史上初めて工業化住宅商品で販売1万棟を達成した。その特徴は大型(O型の由来の1つ)パネルを用いて総2階建としコストを削減しながら、棟や開口部周辺などに独自開発の部品を用いて単調さを脱し平坦な印象を払拭した点、中央入りで両側に部屋を振り分けるプランとしプランも4種類に限定した点、配管・配線を組み込んだ大黒柱や蹴上げの高さを1段ずつ変えた階段などプレハブならではのオリジナリティに富んだ部品群にある(注4)。
ミサワホームO型は、経営者、営業、設計に加えて、ミサワホームが1969年に別会社として設立したミサワホーム総合研究所といった全社的な取り組みの下に開発され、成功を収めた点において貴重な事例である。一方で、1970年代は販売数の増加やTQC(全社的品質管理)の導入等によって工業化住宅の生産体制が大規模化・複雑化し、特定の個人に聞けばある住宅開発の全体が分かるといったことがなくなり始めた時期とも言える。工業化建築も高層建築も当初から比較的大きな設計や開発の組織を必要としたが、そうした体制が整っていく変化や大企業になってコンプライアンスが重視される流れもあり、本音に近い証言を記録に残すことは難しくなり、そうした流れは現在でも続いていると感じる。また、技術開発においても専門分化が進んだ現在では、証言を聞く側にも一定の専門性が必要とされるようになった。
5.どこに価値があるか
最後に、ここまで見てきたような構法に特徴のある建築について何を残すべきなのか、残す意義は何なのか考えたい。例えば、竹中式潜函工法の価値が現在よりも認められていたとしても、地下工法に特徴のあるからという理由で建築全体を残すとはなりにくいように思われる。高層建築や工業化住宅は採算性や実用性を重視する建築であって、高層建築を1棟まるごと残すハードルは高いし、工業化住宅にしても住んでいる人に建て替えないでほしいというのは難しいだろう。さらに外から見ても構法が分からないのであれば、写真や映像、証言を残すのが現実的である。日本相互銀行本店(1952年)の鉄骨フレームやホテルニューオータニ(1964年)のユニットバスのように部分的にでも保存が行われたのは幸運な例なのかもしれない。
そうした中でセキスイハウスA型は軽井沢に残っており文化財として登録された。先述のように、1963年に別荘として建設されたセキスイハウスA型は現在までに大きく改変されて外観ではオリジナルの部品が見える部分の方が少ないとすら言える(写真10)。こうした住宅を残し、そのことについて理解を深めていく意義はどのような点にあるだろうか。
三輪修三は工学史の意義について、以下の4点をあげている(要約は筆者による、原文は注5に記載)。
(1)専門分化した分野の全体像を総合的・立体的に把握する
(2)概念や法則などを所与のものではなく、創造のダイナミズムの中で技術を捉える
(3)技術と社会との関わりから未来への手がかりや幅広い視野を得る
(4)技術者・工学者の生きざまから励みと反省を得る
内容に重複があるようにも思われるが、この視点から見ると、(1)と(2)で強調されるように、セキスイハウスA型や本稿で取り上げたいくつかの建築の価値は「変化のすがた」や「創造のダイナミズム」といった流れの中で捉えるべきものと言える。セキスイハウスA型とB型とを比べて見れば、個別設計への対応といったB型の利点や、A型の手仕事的な特徴も際立つ。加えて(3)にあげるように、セキスイハウスA型からB型への変化や、軽井沢に残ったA型になされた改変からは、プレハブ住宅が一つの普通な住宅として社会や住民に受け入れられていく過程を知ることができる。最後に、「建築があんまり好きじゃなかったし、もうどこでもいいわ注6」と考えて積水化学に入社した石本徳三郎氏がほぼ一人で開発したセキスイハウスA型が、約60年にわたって丁寧に住まわれ残され有形文化財として登録された点から我々は前向きな励みを得るし、そうした励みを得るためにも資料や本音を記録していく必要があると言えるだろう。
注
注1)文化庁HP(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/
shokai/yukei_kenzobutsu~/)2021年7月19日アクセス
注2)荻原行正、RC造超高層建築の躯体構築技術の45年の変遷(連載新時代を拓く最新施工技術第67回)、建築技術2015年5月号、pp.50-57より転載
注3)田中孝、企業のこころ──物語 竹中工務店〈上〉、日刊建設通信新社(建通選書)、1982年
注4)ミサワホームO型については竹内孝治「規格型から企画型へ――商品化時代の幕開け」(日本におけるプレハブ住宅の展開第5回、建築士2021年6月号、公益社団法人日本建築士会連合会、pp.34-37)を特に参照した。
注5)原文は以下のとおり。
(1)現代の技術(産業技術)とこれに関わる工学の範囲と内容は果てしなく広がって、当事者ですら全体が見えなくなってしまった。これは危険なことである。しかし、歴史によってこれらを過去からの「変化のすがた」として捉えれば、全体を総合的・立体的に把握することができる。
(2)重要な工学概念・原理・法則などを「与えられたもの」としてではなく、着想から論争を経て定着に至る「創造のダイナミズム」の中で捉えることができる。この立場の歴史は内部史(internal history)、あるいは学説史といわれる。
(3)技術は社会を変えるが、社会もまた技術のすがたを強く規定する。各時代、各場所で社会は技術に何を求めてきたか、あるいは何を忌避したか、このような「技術と社会との関わり」を歴史の中に見れば、技術ならびに工学の生成・変遷のありさまがわかり、未来への手がかりが得られる。また、人類の文化と文明における技術の功罪について幅広い視野をもつことができる。この立場の歴史を外部史(external history)、または社会史という。
(4)時代を切り開いた技術者・工学者の姿と生きざまを歴史の中で見ることで、ある状況に置かれた個人の決断と行動の正しさと限界、あるいは歴史における個人の役割を知ることができる。これは技術と工学の世界で専門職業人(professional)として生きようとする者にとっては、自分への励みと反省を与える。他方、技術に直接関わりのない一般の人びとにとっても、事を成した人間の生きざまについての感慨はひとしおのものがあるであろう。(三輪修三、「工学の歴史 機械工学を中心に」、筑摩書房、2012年、pp.287-288より転載)
注6)松村秀一ほか、箱の産業、彰国社、2013年、p.65
図版出典
写真1(上下とも)ポルト・デ・リラ:「Systems Building」, Thomas Schmid, Carlo Testa, 1969, Pall Mall, p.219
図1 霞が関ビルディングのキの字の鉄骨:三友かんな作成
写真2 ホテルニューオータニタワー:梅村魁編『建築の施工』丸善、1978年、p.183
写真3 トヨタホームKC型:松村秀一ほか、箱の産業、彰国社、2013年、付録p.19
写真4 セキスイハウスA型:積水ハウス株式会社、積水ハウス50年史 未来につながるアーカイブ 1960-2010、2010年10月、p.11
写真5 セキスイハウスB型:同書、p.19
写真6 椎名町アパート:日本建築構造技術者協会『日本の構造技術を変えた建築100選』彰国社、2003年、p.161
写真7 ローレルスクエア都島:荻原行正、RC造超高層建築の躯体構築技術の45年の変遷(連載新時代を拓く最新施工技術第67回)、建築技術2015年5月号、p.54
写真8 日活国際会館:久徳敏治『技術の竹中・建築構法の航跡』竹中工務店、1989年、p.53
写真9 ミサワホームO型:竹内孝治、「規格型から企画型へ――商品化時代の幕開け」、日本におけるプレハブ住宅の展開第5回、建築士2021年6月号、公益社団法人日本建築士会連合会、p.34
写真10 セキスイハウスA型(軽井沢):積水ハウス株式会社、積水ハウス50年史 未来につながるアーカイブ 1960-2010、2010年10月、pp.30-31